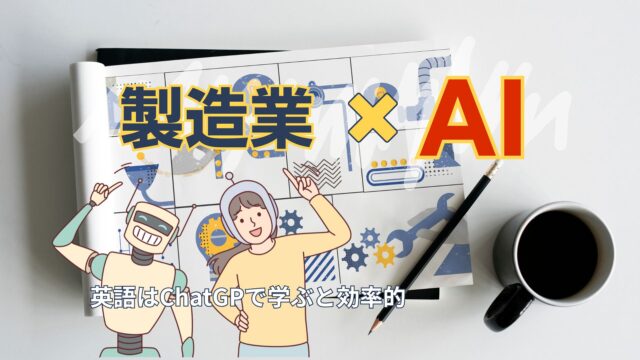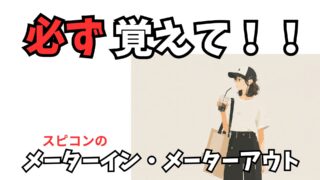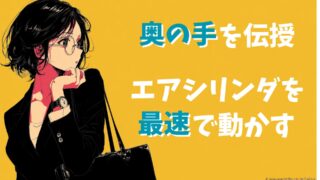【絶対失くさない】150mm鋼尺について【現場あるある】
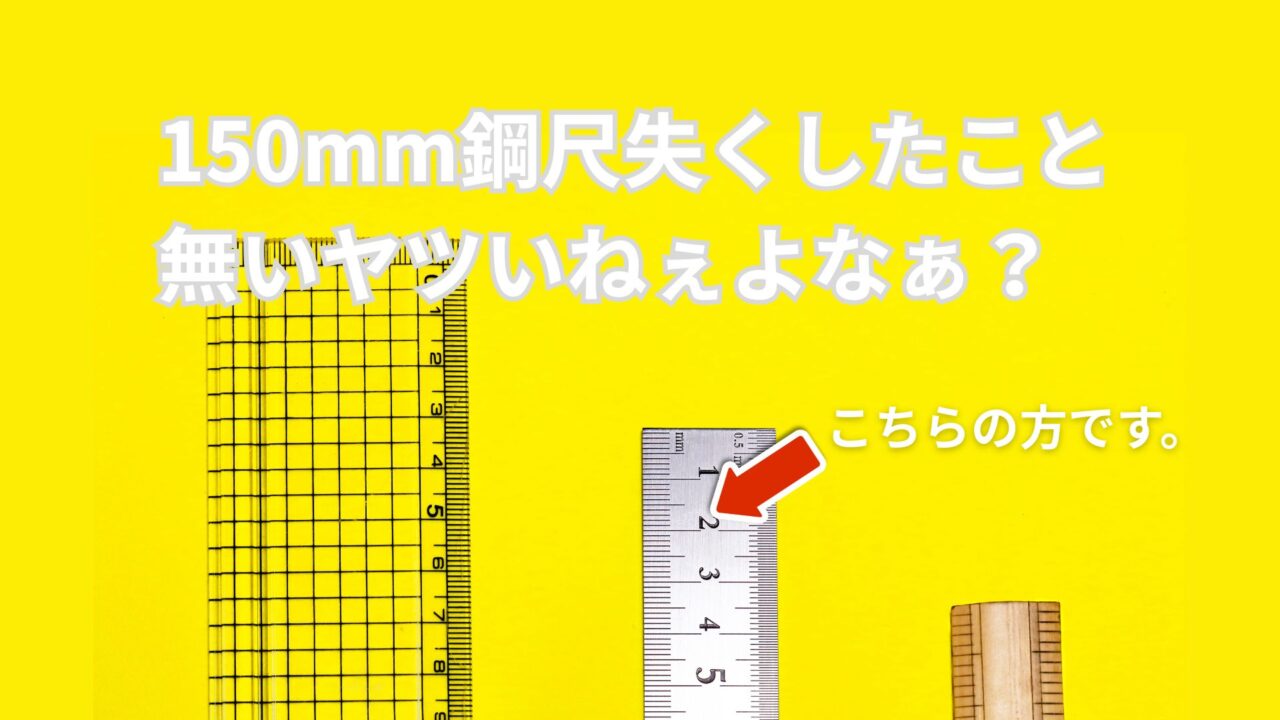
1. 150mm鋼尺とは?現場で使われる理由と用途
150mmの鋼尺(こうしゃく)は、製造業・加工現場で広く使われる最もベーシックな直尺です。
樹脂のスケールやメジャーに比べて薄くて正確。加工寸法の確認、ケガキ作業、寸法読み取りなど、工程全体で使える万能ツールとして多くの現場に常備されています。
特に、ポケットに入るサイズ感と持ち運びやすさ、定盤上でも使いやすい剛性感などが評価され、使い慣れた職人にとっては「これがないと始まらない」存在です。
でも、この150mm鋼尺——実によく無くなります。
私は若かりし日々にタップの下穴サイズを鋼尺に書いてあるものに依存していたので困ることも多かったです。
2. 「あれ、どこ行った?」鋼尺が無くなる5つの理由
■ 理由①:小さくて軽い
150mmというサイズは、作業着のポケットにすっと収まるコンパクトさが魅力ですが、逆に「どこに置いたか分からない」リスクが高いのも事実。軽いので、何かの下に紛れ込むのも一瞬です。
■ 理由②:作業中に“置いたまま”にしてしまう
- 加工機の上
- 検査台
- 図面の上
- ダンボールの中
など、「仮置き」してそのまま忘れて移動してしまうことが非常に多いです。
本人も「また後で戻るから」と思っていたら、もう別の仕事に集中して…いつの間にか紛失。
■ 理由③:隠れる場所が多すぎる
鋼尺は2mm未満の厚みしかないため、紙の間・工具の影・作業台のスリットなどにスッと入り込んでしまうのも問題です。
「目の前にあるのに気付かない」現象、経験した人も多いはず。
■ 理由④:他人が持っていく/共用されがち
鋼尺って、工具箱にあれば誰でも使えてしまいます。
「ちょっと貸して」が常態化し、**誰のものか分からないうちに“どこかへ行った”**という流れは非常に多いです。
■ 理由⑤:「工具じゃない」扱いで軽く見られる
工具のように扱われていない=管理されにくい。
レンチやドライバーと違い、「消耗品だからしょうがない」と思われがちなのも、無くなりやすさの一因です。
3. 筆者の実体験:鋼尺が無くなって困った話
■ エピソード①:納期ギリギリの加工で、鋼尺が消えた!
切削加工中に寸法確認をしようとしたら「いつもの鋼尺がない」。
机の上、工作機、作業台…全部見たのに出てこない。
結局、同僚に借りて事なきを得ましたが、「あの鋼尺がしっくり来るのに…」というストレスは半端じゃありませんでした。
■ エピソード②:定盤の上の“空気”事件
検査で鋼尺を使い、定盤の上に置いて、他の作業へ。
戻ってきたら「…ない」。よく見たら、A4図面の下にピッタリと挟まっていました。
何人も見たのに誰も気付かず、30分くらい探した苦い記憶があります。
■ エピソード③:「工具箱にもう1本…」が5本目になっていた話
いつも無くなるので予備を買っていたら、引き出しに同じ鋼尺が5本。
全部同じタイプ。もはやどれが誰のか分からない。
最終的には名前を書きましたが、「最初からやっとけば…」と思ったものです。
4. 無くさないための現実的な工夫と対策
■ ストラップやマグネットホルダーの活用
- クリップ付きホルダーを胸ポケットに装着
- マグネット付き鋼尺ホルダーを作業台に固定
- 腰袋や工具差しにスッと差せる専用ポケットを用意
物理的な定位置を作るだけで、無くなり率は激減します。
■ 鋼尺に名前・色・マーキングをする
- 油性マーカーや刻印で自分の印をつける
- シール・テープで目立つ色にする
- 工場内で「マイ鋼尺制度」を設ける
個人所有として認識されれば、他人が持っていく心理的ハードルが上がります。
■ “鋼尺定位置ルール”の徹底
- 毎日終業時に「鋼尺が戻っているかチェック」
- 作業台に「ここに戻す」表示をつける
- ポケットを“鋼尺専用”にして、他の工具と混在させない
チーム全体でルール化すれば、習慣にするのも難しくありません。
■ 「貸出制」や「一括管理」も選択肢
- 1人1本を支給・登録し、持ち出し管理
- 定期的に数を確認して、紛失防止の意識付け
- 使用記録や備品台帳で“所在管理”をするのも◎
5. まとめ:たかが鋼尺、されど鋼尺。無くさない意識が“信頼”につながる
150mmの鋼尺は、たった数百円の工具です。
でも、それを無くすと「信頼」「段取り」「集中力」が一気に削がれます。
- 作業効率が落ちる
- 作業者の焦りがミスを生む
- “また無くしたの?”という空気が職場に広がる
小さな道具を大事にできる人が、現場全体の精度を守る。
150mmの鋼尺を無くさない努力は、単なる道具管理ではなく、
“仕事の丁寧さ”そのものを表す行為なのかもしれません。だからこそ今日から、「いつも使う鋼尺には居場所を作ってあげる」。
それだけで、現場の空気は少しずつ変わっていきます。